http://ushikunumakankyo.my.coocan.jp
�z�[��
| 2025�N1��27���X�V Le soir de la vie apporte avec soi sa lampe.--Joseph Joubert |
 |
2025.01.25 �@NHK��̓h���}�ł́A���݂́A�������肳������Ή��ł���������Z���Z�[�V���i ���E�W���[�i���Y���́A�c��Ƃ������ׂ��A�o�ʼn���J�ߏ̂��Ă���B�]�˂̐��Ƃ� �ʂƂ�����Ƃ��ݏo�����̂��A�K���̍]�ˏW���ƁA���̊K���̎��v���� ���Ȃ����߂ɏW�܂����l�X�A���̈ꕔ�̐��~���[�������߂ɔ���ꂽ�n�� ��H������ ���Ă����l�X�ŁA�Ƃ��Ă��J�ߏ̂��ĉ�ڂ��ׂ��ł͂Ȃ��ƁA�v���i�������A�u�]�� �����v���]������l�̂ق��������̂ŁA��Ώ����ӌ��ł���j�B��N�́A��������� �̃I�}�[�W���ԑg�ŁA��������͐��E�Ɍւ���{�����̑�\�Ƃ������ƂɂȂ��Ă� ��B���A�ȂɁA�命���̚������u�a�ƍЊQ�Ƒd�łɋꂵ��ł����̂����ėV�щ� ���Ă����ꕔ�����K���̐F�������̕`�ʂɂ����Ȃ��悤�Ɏv����B���̐Q�a����Ƃ� ��V���뉀�Ƃ����A���E�Ɍւ���{�����ɍ��͂Ȃ��Ă��āA�u�C���o�E���h�i�C���� ���t���j�v�Ɍւ炵���Ɍ����Ă܂����҂�������ƂɂȂ��Ă���B���~�D�Ɉ�� ���ꂽ���̖�́A���ꕶ���̌ւ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A����̂Ȃ��ŗV��� ���������́A���d�R�ȂǗ̒n�̐l�X��h�Y�̋ꂵ�݂ɒǂ�����Ă����`�`�ȏ���A�� �Ǝv�����̂́A���܂��܉��{���Y�́u���d�R�̔߉́v��ǂݒ���������ł���i���{ ���Y�́A�G��ƑY���̍�i���A���͂��悢�A�Ǝv���j�B���������A�̂̑�̓h�� �}�ł́A�F���ˎm���]�����Ă������A�����哇�ȂǎF���˂ɋs�����Ă����l�X�̋� ��́A���̎R�̓����ɂ͏�����Ă��Ȃ��B�Ƃ͂����������A���{���Y�́A�ߋ��� �l�X�̋�J�����݂̐l�X�̎蕿�ł��邩�̂悤�Ɍ����Ĝ�Ă͂����Ȃ��Ƃ����_�� �����Ă���B���łȂ���A���̘J���̒��ł̂��肬��̋��ѐ��̉������|�p�ŁA ���ꂱ��Ɖ��y��m�Ɏc���Ă��镶���Ȃǂ͔r�����ɓ������Ƃ������Ă���悤�� ����B�������Ƃ���A���̑��z�̓����A���{���Y�̐����������ʐl�X�ɂ́A���p�� �p�Ђł���B�p�Ђ���邽�߂̖������A�܂��J����悤�Ƃ��Ă���`�@�́A��㖜�� �ɉ�����l�X���Ƃ܂邽�߂̃��[�X�z�X�e���̊Ǘ��l�������Ă�������A�� ��Ɉ�t�Ƃ��ĕ��C���Ă���������v���o�����̂ŁA�Ƃ��ɂ���������Ă��܂����B ���ꂩ��50���N���������B�c�O�Ȃ���A�]�ˎ���͂܂������Ă���B�n���Đ������ �ߑa�n�o�g�̑�����b�ł��A��������̑J�s�͌���Ȃ��A�����Ȃ��A�����Ă����̑O �ɃZ���Z�[�V���i���E�W���[�i���Y����SNS�`�_�Ȃǂɂ���ĕ�������邾�낤�B�� �����肳������Ή��ł���������Z���Z�[�V���i���E�W���[�i���Y���Ɠ������炢�| �낵���̂́A���`�̂��߂ɂ͉��ł������A�����A����l�X�ł���B���яG�Y�́A���� ���Ԃ͂��邪�A�Ԃ̔������Ƃ������̂͂Ȃ��A�Ɗ��j�����B���`�̐l�͂��邪�A���` �Ƃ������̂͂Ȃ��B���`�̐l�́A���́A�Ȃ����`�𗝗R�Ƃ��āA�l������l�ł���B �c�c�b�͔�Ԃ����{���Y�͌|�p�͔������A�ƌ������B���z�̓��͎������e��������� ���c�c�Ƒz�����Ȃ���A����͉��{���̎q��ǂށB |
 |
20240610 ���̂Ƃ��������������B����́A�{���͖{�l�̐��� ���o���������A�킴�킴�����ŏo����Ă��邱�Ƃ�����̂ŁA�o���� ���B���w�Z���獂�Z�܂ł̓������ł���A���w�Z���w�Z�͂Ƃ��Ɋw�Z�� ��100���[�g���ȓ��������̂ňꏏ�ɓo�Z���Ȃ��������̂́A���Z�͖� ���ꏏ�ɓo�Z�������Ă̐e�F�̌������ɓ����Ă���̒��ł���B�� �Ír�ہw���ɂ����̎U�����x���~�ɁB�Î��L�A���{�I�A�����j����T�� �Ƃ��������ꂽ�A�Ñ���{�_�ł���B���͌Ñ���{�͂܂������m��Ȃ� �̂œ��e�̕]���͂ł��Ȃ��B���҂��w�Z�ł̐���E�ƂƂ͒��ڂ̊W ���Ȃ��B���I�ȃ��C�t���[�N�ł���B�b�͔�Ԃ��A��NHK��̓h���} �ŁA�ԕ�Q�m�����グ��ꂽ�ǂꂩ�̃V���[�Y�ŁA��Γ��������A�� �����Q������̂��Ɩ���āA����Ȑl�Ԃ������Ƃ������Ƃ��㐶�ɒm �点�����Ƃۂ�ƌ����V�[�����������B�Ɍ����悤�Ȗ����㐶�� �c���A�Ƃ����悤�ȈӖ��ł͂Ȃ��Ǝv���B�܂��ɘ_����Ή������Ȃ��� �����̍��Ղ͂��̉F���Ɏc��̂��Ƃ�������B���A���������N�w�v�z�_ �c�͖������āA�ӎv�������ĉ����������Ă����̂́A�������ƂȂ� �Ȃ����ȁA�Ƒf���Ɏv���āA��l�Ɋ��߂邱�Ƃ����̕ȂƂ��Ă͂��� �i�����̒n�ʂĂ����Ղ�Ǝ��ԂƋ���������Ă���̂ɐ��U�قƂ� �ǒ������o���Ȃ��A�������Ă��������Ɂ`�Ƃ������Ȏv��������͎̂� �̌��_�ł���B�������𗧂đ����ɏo���Ƃ����Ӗ��ł��Ȃ��j�B �ʗ_�J�Ȃ͑��l�ɔC�����낵���B�܂��܂��b�͔�Ԃ��A���������� ��Ƃ̒����ɓ��{����������Ƃ��̊ՉɂɁA�n���̌Ö{���ŁA�n���ɐ� ���Ă����l�̌l�o�Łi�����j�Ƃ��Ƒ��j�Ƃ��n��j�Ƃ��A���Ă܂��� �̂Ƃ��j�̖{�̃R�[�i�[������ƁA���łP�C�Q�����߂邱�Ƃ������� ���`�����āA�����Ύ����̌����ɂ��𗧂̌��k�����āA��d�O �d�Ɋ��ӂ��������Ƃ�����B����͎��֓͂����g��̏ꍇ�����A�l���� ����g��́A�������������Ȃ��Ǝv���i�l�����ł͂Ȃ��j�`�����Ȃ�� ���E�ς�����A�ڍׂ͋c�_���Ȃ��B�Ȃ����O�������A��Â���̒��� �����̏��ŁA�Ƃ��Ɍ̋������v���o�����p������B��������́A���c ���K�w�[�l�����X�g�̐l�ވ琬�E�\�͊J���x�����o�ώЂł���B�e�[�} �́A���̂��Ă̌������ɋ߂��̂Łi�����Ƃ������10�N�A�����͎~ �߂��̂ŖY�p�̂��Ȃ��ɂ���Ƃ͂����j�c�_����ƒ����Ȃ�̂ł�߂� ���A��w�E������N���N���āA�Љ�l��w�@�ɒʂ��ďC�m���āA�� ��ɔ��m�ے��ɐi��ŁA��w�����ɂ܂ŃL�����A��[�߂��A�w�F�̔��m �_���ł���B�ӂ��̑g�D�l�̐l������l���A�g�D�l�̌��������� ���Ɏc���͍̂D�܂����i�A�t�^�[�t�@�C�u�́A�T�����[�}��OL�̕��� �Ȃ���̂́A���O�`�ƈԂߍ����ŏI��肽���̈��݉�ƕς��Ȃ� �`�܂����������l���������Ȃ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��`�P���Ȃǎ��ɂ͌�� �Ȃ��j�B�����邱�Ƃƌ�邱�Ƃ͕ʁA�Ɣ��Ō�邱�Ƃƕ������Č�邱 �Ƃ͕ʁA�������Č�邱�ƂƘ_���I�Ɍ�邱�Ƃ͕ʁA�_���I�Ɍ�邱�� �Ə؋��������Č�邱�Ƃ͕ʁA����Ɍ�邱�ƂƏ������Ƃ͕ʁ`�K�i�� ���ނ��Ƃ͑�ς����A�K�i����邱�Ƃɐ��������������Ƃ͂悢���� ���낤�i�ʂɒ������o���҂��̂��ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�������o�� �ʂ܂܂̐E�l���̂����A�v������t�̐�[�ɏ����c�������炱���A ���D�l�ˈ�̌��t�͑����̐l�̋���ł����B�������l�̋������Ƃɐ� �����������o���Ƃ�������ł͂Ȃ��j�B��������A�h�A���J����� ���Ƃ�����B�ǂ��ւ��͏ꍇ�ꍇ�B�b����Ԃ悤�����J���Z�Y�w���̊G �{�x���Ö{����100�~�œ����B�Ȃ��Ȃ��钼�O�̂��̂��B�́A�X���E �����W���[�i���Y���ɓ�������O�̏T�����̕\���Œ����ŁA�����\���� �������Ė������o��������B�u���Ƃ����v�ɂ�������|�|�u���w�Z ���o�āA���炾�����������̂Œ��H���]�X���܂����B�a�C�Œ����x �ނƃN�r�ɂȂ�̂ŁA�]�X�Ƃ����킯�ŁA�������ƁA����ʊy�������� �����Ƃ������Ƃ͂���܂���B�a�C�ŐQ�Ă��鎞��肩�A�ǂ�Ȃɂ��� ���I�Ȃ��̂�������������܂���B���A�����݂��݂Ǝv���̂͂���ȏ� �N���Ɏd���������ĉ���������y�̐l�X�B�{���ɗ܂��o��قNJ��ӂ��� ���B�d���������Ă��ꂽ�A������т������Ă��ꂽ�Ƃ������̐�y�� �l�X�ł��B�ڂ��͂����̐l�X�̊�N���鎞�Ɏv���o���̂ł��B�� ��Ƃ��̓���������S�ʼn߂�����̂ł��c�c�c�c�v�B���S�P�`����͊w �Z�����ōs������̂ł͂Ȃ��A���S�Q�`�v�����^���A���w���獡���� �w�ҁE�W���[�i���Y���̈ꕔ�ɂ�����܂ŁA���邢�͘J���Ҏ��g�̈ꕔ �܂ŁA�E���n����������l�X�́A���Ă��Ȃ����������A���S�R�`�� �N���[�g��r�Y���[�`�Ȃǂɂ��������ĐE���]�X�Ƃ���l�X�͖{ ���ɗ܂��o��قNJ��ӂ������l�X�̂���E��������₢�Ȃ�B���S �S�`���N���鎞�Ɏ��͊��ӂ��ׂ��l���v���o���Ă���₢�Ȃ�B������ ��̃h�A���J���Ă݂Ȃ���Ȃ�܂��i���ȁH�����������ق����K�� ���ȁH�j�B |
�ȉ��A�o�ŕȊO�͋ߋ��Ɉڂ��܂��� |
| 2021�N8��1���@ |
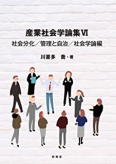
�w�Y�ƎЉ�w�_�W�Y�@�Љ���E�Ǘ��Ǝ����E�Љ�w�_�ҁx���A�}�]���݂̂ŁA�����A�̔����Ă��܂��B�y�n�Z��Y������i���ɂ��Љ���A�J���҂Ǝ��c�Ǝ�̍�����ɂ�����Ⴂ�A���c�ƍ���ғ����̐E�Ɛl���o���ɂ�镪���A������ƘJ���҂̕����A�Ƃ�킯���K�͊�Ə��������E�̎��Ǝ҂̋����ȂǁA����܂ł̘_�W�ł݂Ă����Љ�I�����̑��l���Ŏ��^�����炵�����̂ł��B�J���҂Ƃ��o�c�҂Ƃ��A�����J���҂Ƃ��A������ƘJ���҂Ƃ��A����҂Ƃ��A�T���ĎЉ�W�c�l�Ɍ��錩���͋ȕ��ϑ������킩��Ȃ��Ǝ��͎v���Ă��܂����B�㔼�͍��܂ł̒����̂��̂ƈႢ�A���_�E���������ł��B�Y�Ƒg�D��E��W�c�A�͂��܂��n��ɂ����閯�吧�ւ̊��҂�^���ƌo�c�Ǘ��̓s���Ƃ̒��a�̓���𗝘_�₢�����̗��j�o������_�l���A19���I���ȗ��̃f���N���V�[��]�_���܂ߗ��O�_�ł��Ƃ����Ƃ���������ɑ�����؎�`�Љ�w�҂̋c�_��ǂ��Ȃ�����A���̎Љ�w�҂ɂ��܂��g�D�l�̐l�ԓI�~���̔��I�̉\����ǂ��p���̋��������l�����āA�܂����}�⍑�ɂ��Љ�����������Ɋ��҂���Љ�^���̊댯�����������܂����`�Ƃ͂����������40�N�O�̘_�l�W�ł��B���ƂȂ��Ă͖��ʂȋc�_��������܂���i���e��HP�̖ڎ��W�������������j�B
| 2020�N6��10�� |

�w�Y�ƎЉ�w�_�W�X�@�l�ސ헪�E�ƊE����ҁx��V���ɂ���o���܂����B�A�}�]���݂̂ŏ����A�̔����Ă��܂�(���܂܂ł̃V���[�Y���l�A�����W�ł��j�B���a�������畽���O���̐l�����x���v�A�g�D�̖��͂ɉe������v���A���l�Ȑ��x���v�I�����A�x���`���[�����ƁA�ό��T�[�r�X�ƁA���ƁA�g���b�N�^���ƁA�����ƁA���e�X�ȂǁB���_�E���f���E��ʉ��͌����ł�����A�����Ă܂���B�Y�ƎЉ���x���鑽�l�Ȑl�X�E���������邢�͓��������B�g�D���l�������w�͂���̂݁c�c���B�Љ�w�̋��ȏ��ɏ����Ă��邱�ƂȂǁA����܂点��̂ŁA�������Ă悩�낤�B�ꎞ��̎j���܂��͎����Ƃ��āB�u�ߒ��ڎ��v�̃R�[�i�[�����Q�Ƃ��������B
| 201�V�N�S���R�O���@ |
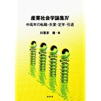
�w�Y�ƎЉ�w�_�W�W�@�����N�̓]�E�E���ƁE��N�E���ށx��V���ɂ���o���܂����B���̖{�Ɠ��l�A����o�łŔ���錩���݂͂Ȃ��A�A�}�]���݂̂ŏ����A�̔����܂�(���̃V���[�Y�̑��̂R�����l�A�����W�ł�����A�u�ދ��v�ł��B�ʔ����������͂���܂���B���_�E���f���͌����ł�����A�����Ă܂���B���m�ł��������߉�����)�B�]�E�E���ƂƂ����Ύ�N�҂̃t���[�^�[���̃j�[�g���̂��b��ł����A�ȂɎ�N���ƁE�]�E�͐̂���b��B���ǂ̂Ƃ���債�ĖڐV�������Ƃ��Ⴀ��܂���B�����蒆���Ȍ�̑g�D�l�̑I���Ƒg�D����̑I�ʂ̂ق��������ɂ͋���������܂����B���ǂ̂Ƃ���A�����̍��͐r�������A�Ⴆ�A�������ƂŒ�N���}������A��N�O�ɏo����𐢘b���ꂽ�l�Ɨ��Ƃł̎��Ƃ��J��Ԃ����l�Ƃł͘V��̊i���͑傫���B��N�҂�q�ǂ��̕n���ȂǍ�����C���������f�B�A����قǕ����Ă����̂ł��傤�B���Ƃ̏����̎��Ǝ҂�����A�d�v�Ȗ��͒j��������Ȃ��B�����Ԃ̊i�����傫���B�g�D�̑I�ʂ́A����������苭�܂��Ă���ł��傤�B�J�g�����đ命���̊Ǘ��E����J���҂ɂ͖����̑��݁B�������ʂɎ��Ƃ��Ă��������̐l�̐��́A������O������̂��A���f�B�A�͓`���Ȃ��B���ǁA�F�A�����̃L�����A�͎��q���邵���Ȃ��B���G�ɑI�ʂ��Ȃ��D�ǂȒ�����Ƃɂ��܂��]�E����A�C�f�A�����A�����̐l����Ⴂ�܂����B
| 2016�N10��27���@ |

�w�Y�ƎЉ�w�_�W�V�@��Ј��̋����ƐS��ҁx���ΘJ���ӁiLabor Day�j�̓��ɏ����I���A�V���ɂ���10��26���ɔ��s���܂����B����3000�l�߂��T�����[�}���AOL�ւ̃A���P�[�g�������ʂ̍Ę^�ł��B��㍬�������獂�x�������x���A�o�u���o�ς̕���܂ł������l�X�́u�S��v�̈�[�ł��B���_�����f�������������̌n������Ⴕ�܂���A�ꎞ����x�����l�X�̐��́A���̈����^���@�ɂ���^���B���̘V�オ����̂������Ɩ�����œ����Ă����l�X�̂������B��͂̐g�A���̕��ł��Ȃ������B�������ӂ���̂݁B
| 2016�N3��15���@ |

�w�Y�ƎЉ�w�_�W�U�@������ƂƂ��̌o�c�ҕҁx���S��12���ɐV���ɂ��犧�s�AAmazon�Ŕ̔����Ă��܂��B�n��Y�Ƃ��牵������A�h���Y�ƁA�\�t�g�E�G�A�ƃA���P�[�g�����ŏ��Ă����L�^�ł��B�ł��邾���Ǝ�����肵�܂����B������ƈ�ʘ_���ł��Ȃ����̍\���̂����ł��B�ꕔ�A����Ȓ��܂܂�Ă��܂��B���̌�̕ω�������ƍ���̂ł����A�ꎞ��̊ώ@�҂̊�̂܂܁B
| 2015�N12��10���@ |

�w�݂�@��ށ@�킩��@���_��w����x�i���c���Ė�j�ɋ���҂Ƃ��ĎQ�����܂����B��������w�͑f�l�ł����A���|��i�Ȃǂɂ݂�S�̓����Ɋւ��Ƃ���́A���ĕ��w���ɑ������肻�̌���o�c�S���w�̖{��ǂ�ł����̂ő����v���ł������Ǝv���܂��B�����T�V�搶�Ƃ̉��ł��B
| 2015�N10��20���@ |
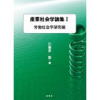
�w�Y�ƎЉ�w�_�W�T�F�J���Љ�w�����ҁx��V���ɂ��犧�s���܂����B��Ƃ���amazon�Ŕ̔����܂��B1980�N������20�N�A�����̉����ݒ�����˂ď����Ă������́B���a�͐̂ł����Y�ƎЉ�w�A�J���Љ�w�Ƃ��ɐ�Ŋ뜜�킾�ƕ����܂������A�V�̎S�ł��̂ŁA�����Ă܂Ƃ߂܂����B
| 2015�N8��15���@ |
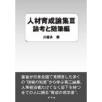
�w�l�ވ琬�_�W�V�F�_�l�Ɛ��M�ҁx��V���ɂ��犧�s���܂����B1985�N�������30�N�A����ɂӂ�ď����Ă������̂ł��B����ɗ�����A�����������Ƃ���������Ă��܂������A��l�́u����̖T�ώҁv�̐��_�ł��B�A�}�]���Ŕ̔����Ă��܂��B�Ȃ��l�ވ琬�_�W�V���[�Y�͊���̑�w�Ɋ�t�����̂ł��������قǂ���͎����ꂸ�p�������ɂȂ�܂����B��_�䂦���Ǝ����Ȃ�ǁA�l�ވ琬�_�A�s�p���Ȃ��E�E�E���J��f���Ɂu�V���̊�J�̂ЂƂԗ����ɂ���v�Ƃ����傪����܂����u�V������J�̑S���K�ꂸ�v�Ƃ����C���ł��ˁB
| 2015�N7��15���@ |

�w�l�ވ琬�_�W�U�F�u���L�^�ҁx��V���ɂ��犧�s���܂����B�w�l�ވ琬�_�W�F������ƕсx�̑��҂ł��B1990�N���납��2010�N���炢�܂ł́A20��̍u���L�^�ł��B������Ȃ��玞��̕ω��ɋ����܂��B����ɗ�����ď��q�ׂ������ɂ͒p���炢�������܂����A��т��Đl�ވ琬�̑���������Ă����悤�ȋC�����܂��B�r�̉��i���ł����B���\�ȋc�_�ł����A�悯����������������B
| 2014�N8��10���@ |

�w�g�D���v�_�W�F�J���g���ҁx��V���ɂ��犧�s���܂����B�O���I���̎Љ�ϓ��ɑΉ�����J���g���̑g�D���y�v�V�Ɋւ���A�_�]���܂Ƃ߂����̂ł��B���������Â��c�_�ŋ��k�ł���Amazon�Ȃǂł����߂��������B
| 2014�N4��10�� |

�Ė��wIBM�̃L�����A�J���헪�|�ω��ɑ�������l���Ǘ��V�X�e���̍\�z�|�x�����F�ق��犧�s���܂����B�A�����J��IBM�{�ЂŃL�����A�x�����x�̗��ĂɌg����������҂ɂ�鎖�ጤ�����A��Ɛl���ԂƋ��܂����B
| 2013�N3��25�� |
 |
�w���C�Ȓ�����Ƃ̐l�ރ}�l�W�����g�x�F�ق��犧�s���܂����B1600�Ђ̖K�⒲���̏W�听�ŁA�P�O���Ђ̃P�[�X�����ƁA�����̎��Ⴉ��́A���Ȃ�́A������ƌo�c�ҁE�Ǘ��Ҍ����̋��P�W�ł��B |
| 2013�N10��20�� |

�w�d���Ƒg�D�̋��b�W�|�t�N���E�̒m�b�|�x���V���ɂ���ĔłɂȂ�܂����B�d���E�g�D�E�l���Ɋւ�鐏�M�W�ł��BAmazon�ł����߂��������BKindle�ł����킹�Ċ��s���܂����B
| 2013�N11��15�� |

�w�Љ�����C���[�Z�@�ȑO�̘b�[�x��V���ɂ��犧�s���܂����B��Ƃ���Amazon�ŁA�d�q���Дł��܂ߔ̔����܂��B���̐E�Ɛl���̏W�听�ŁA�Љ�����̋C�\���A�����Y�Ƃւ̔ᔻ�A�����̕i���Ǘ��A���_���Ă��܂��B�����Z�@�͏����Ă���܂���B���I�Ȉ����G���ɖ����Ă��܂��̂ŐԖʂ̎���ł����B
| 2013�N12��7�� |

�w�l�ވ琬�_�F������ƕҁx��V���ɂ��犧�s���܂����B��Ƃ���Amazon����A�d�q���Дł��܂߁A�̔����Ă��܂��B���܂ŏ����Ă����l�ވ琬�_�̂����A������ƂɊւ�����̂��W�听���܂����B25������65�܂�40�N�ԁA�ق�1600�Ђ�����ċ������Ă������Ƃ̏W�听�ł��B���Ƃ��܂��X�̐E����Ƃ�Β�����ƂƓ�����������܂���B���Ⴊ���S�ł��̂ŁA�Q�l�ɂȂ邩������܂���B




